おはようございます。
梅つま子です。
先日、大学院時代の仲間2人と『暇と退屈の倫理学』の読書会をしました。
合計3人の、小さな読書会です。
無事、読破できました…!
ちなみに読書会は、互いに遠方に住んでいる3人なので、読書会の方法、zoomにする?skypeにする?と言ってたのですが、仲間の一人のPCが使えなくなり、LINEのグループ通話になりました。
1時間という限られた時間だけではあったし、音声だけでしたが、十分に、できました!

- 読んだ本の紹介
- この本をこう読んだ
- 私は、暇じゃないけど退屈している
- 公園にいると、退屈
- ワーママとしての環世界、専業主婦としての環世界
- 「もったいない問題」再び
- 退屈は、忌むべきものじゃなくて
- で、どうするか
- 終わりに…一行感想
読んだ本の紹介
暇と退屈が、あらゆる角度から論じられてる哲学書です。
なにしろ437ページある大著なので…詳細は、商品説明↓からどうぞ!
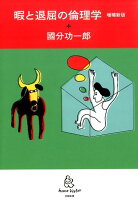 |
國分功一郎 太田出版 2015年03月 売り上げランキング :
|
ちなみにこの本、アマゾンで買うとプライム対象ではないので送料がつくのですが、楽天ブックスでしたら送料無料でした(2019年4月5日現在)。
旧版ならアマゾンでも送料無料なんですけど、なぜ人間は退屈するのか、について書かれた「傷と運命」という論考が所収されてないのです
なので、買うならこっちの白いやつじゃなくて、こっちのカラフルな表紙のものをお勧めしておきます。
この本をこう読んだ
3章に、「暇と退屈の類型」が出てきます。
そこに「暇がある/暇がない」「退屈である/退屈でない」の2つを軸に、
- 暇があり、退屈である
- 暇があり、退屈していない
- 暇なく、退屈している
- 暇がなく、退屈していない
の4パターンの人間が区別されています。

この、「暇がなく、退屈している」って、まさに自分の問題ではないのかと思ったんです!
家事育児で忙しく、時間も余裕もまったくないのに、どこかで自分の退屈をもてあましている、満たされてないのは、まさに私ではないかと!
かつ、ワーママのときってこの退屈さがなかったように思われる。
だから、私の問題に当てはめると、こう。

なんとなく今もやもやしているこの感じが、少しでも解けるかな?
そんなふうに期待して、本書を読み進めました。
私は、暇じゃないけど退屈している
まずは、私の現状から。
家事、育児には終わりがない。
炊事だって、掃除だって、洗濯だって、子どもの世話だって、もっと「丁寧」にやろうと思えばやれる。
どれだけ丁寧にやったって、まだ「やり残し」はある。
時間はどれだけあったって、足りないはず。
だから私はとても「暇」だなんていえない、です。
実際、そこまで突き詰めなくたって、テキトーにやっていたって、暇なんてなくて。
5歳の女の子を幼稚園に行かせて、常に傍らには2歳の男の子がいる。
朝ご飯の支度と同時にお弁当をつくり、子どもを着替えさせ、食べさせ、子どもを幼稚園まで送っていったら、洗濯して掃除。
自分と息子のご飯を食べて、食料・日用品の買い出し。
幼稚園に迎えにいき、子どもの世話。
晩御飯の支度をしておき、スイミングに連れて行き、帰宅したらご飯を食べて、お風呂に入れて、寝かせる…。
そう、専業主婦は暇じゃない、はずです。
でも、なんだか体感として「退屈である」と感じることはよくある。
だからこそ、私はなんとしても日常の隙間を縫って「気晴らし」を探しているんだと思います。
お友達を探しておかず会をしてみたり。
ウクレレサークルを立ち上げてみたり。
そもそもこの本を読んでいるのだって自分が「退屈」だと自覚しているから。
「今ここにある、退屈さ」から自分を奪い去ってくれるような気晴らしを見つけたくて、私はいつも探してるんです。
その結果、毎朝ブログを書くという生活になっているわけです。
公園にいると、退屈
本書によると、退屈は2種類あって(ハイデッガーの退屈論によって説明されている)、
①何かによって退屈させられること
②何かに立ち会っているとき、よくわからないのだがそこで自分が退屈させられてしまうこと
なのだそうな。
(太字強調は梅つま子によるもの。以下同様)
退屈においては時間がのろい。時間がぐずついている。
(『暇と退屈の倫理学』p.219)
私たちは退屈しながら、ぐずつく時間によって引きとめられているのである。
(『暇と退屈の倫理学』p.220)

これは、公園で子どもの遊びの終わりを待っている私のことでしょうか
「時間がぐずつく」「引きとめられている」って表現、めちゃくちゃよくわかるんですよね。
公園で子どもの遊びが終わるのを待っているとき、私は、
早く家に帰って、家事がしたい!
早くご飯の支度をしたい!と考えています。
そして無事に帰宅すると、今度はご飯の支度がしたくなくなる、という仕組みにもなってるけど^^;
自分にとって「公園で子どもと一緒に遊ぶ」ことがうまくできることではないから、「退屈だ」と感じるのでしょう。
そこには物がある。
しかし、それらのものがこちらに向かって何事も仕掛けてこない。
私たちを完全にほったらかしにしている。
(『暇と退屈の倫理学』p.222)
そう、物は目の前にあるのに、自分には何も仕掛けてこない。
公園のブランコも、滑り台も、私に働きかけてはこないんですよねえ。
物にほったらかしにされている感じ、よくわかる。

だから家に帰りたくなる
そして…仕事がしたいな、大人と話したいな、と思うのも、そんなときだったりする。
ワーママとしての環世界、専業主婦としての環世界
自分の経験とか、性質なんてものを考えたうえで言ってみると…。
子どもと遊ぶより、家事していたいし、もっというと、学問したり働いているほうが好きだなと、正直なところ思う。
それにしてもなぜ退屈している私たちは、やるべき仕事を探し、仕事に従事しようとするのだろうか?
仕事というのは普通、できることならやらずにすませたい、そのようなものではないのだろうか?
いや、そうではないのだ。
やるべき仕事がないと、人は何もない状態、むなしい状態に放っておかれることになる。
そして、何もすることがない状態に人間は耐えられない。
だから仕事を探すのである。
(『暇と退屈の倫理学』p.221)
本書で出てくる「環世界」(p.270)という概念は、「ワーママだったとき楽しかったな」と思う自分を説明するために有益なキーワードでした。
環世界というのは、それぞれの生物が生きている世界のこと。
環世界(かんせかい、Umwelt)はヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念。環境世界とも訳される。
すべての動物はそれぞれに種特有の知覚世界をもって生きており、その主体として行動しているという考え。
ユクスキュルによれば、普遍的な時間や空間(Umgebung、「環境」)も、動物主体にとってはそれぞれ独自の時間・空間として知覚されている。
動物の行動は各動物で異なる知覚と作用の結果であり、それぞれに動物に特有の意味をもってなされる。
ワーママとしての私が生きていた環世界と、専業主婦としての私が生きている環世界は、空間のあり方はもとより、時間の流れが違う。
ワーママの環世界は懐かしい。好きだった。
どうやって会議資料を作ろうかなとか、いつまでにお弁当発注して、書類作って、必要な箇所に連絡して…とか考えて、細かい細かいタスクをいくつも達成している間に半日終わってる感じ。
あのスピード感。
自分の価値が発揮されてた気がする。ワーママの環世界では。
「1時間、公園にいて、子どもの遊びを見守る」なんていうのは、専業主婦の環世界ではざらにある。
けど、ワーママだった私は、ワーママの環世界での時間の流れ方に慣れている私は、
「1時間、ただ公園に立つ…何の成果も出さず?!」
とか思ってしまう。
だからつい…子どもを見ながら公園でもできる筋トレって無いかな、とかそんなことを考えるわけです。
ワーママの環世界にしばらく身を置いたあとに専業主婦になったおかげで、ネットショッピングがうまくなったり、効率的な家事を考えるのは好きになった…かもしれない。
しかし、私も認めなきゃいけない。
私は今、ワーママ時代を美化しているんでしょう。
もはや記憶にも薄れてしまったけど、ワーママ時代、退屈と無縁だったわけじゃない。
自分にまったく関係のない、少なくとも発言できる事項がひとつもないと感じている会議に拘束されてて、退屈を感じてなかったわけがないんだよな…。
そのとき、子どものことを考えなかったかというと嘘になる。
そもそも、その組織に所属するフルタイムの労働者として会議に参加しているのに「自分にさしはさめる余地は何もない」と感じることこそやばいだろう。
よしんば「退屈」とは名づけにくいものだったとしても、ストレスとか無力感とか…退屈よりもよっぽど危険な何かに付きまとわれていたことも、忘れてはいけない。
「もったいない問題」再び
話は変わりまして。
大学院を修了して大学に職を得て、キャリアを築き始めた矢先に退職したことを、多くの人に「もったいない」と言われてきました。
そのたびに、「あなたの選択は賢明ではない」と言われているような気がしていました。
この「もったいない」に、何度となくカチンときたんだけど、本書を読んだことで、「もったいない」と「退屈」って似てるかも、と思えたり、「もったいない」を「環世界」をくっつけたりして考えることができたんです。
すなわち、「退職して、もったいない」を、「退職して、退屈でしょう?」と読み替える。
「忙しかったワーママ時代に比べて、することがないでしょう?」
「ワーママだったあなたが専業主婦をすると、時間がぐずつくでしょう?」
「専業主婦としての環世界では、あなたの周りの物はあなたに働きかけてこないでしょう?」
と言われてるとしたら、納得がいく。
そして、その答えは「はい」でもあるけど、どちらかといえば「いいえ」なんです。
「はい」だと思うのは、前述の、公園での私の例のように、自分の能力が発揮できている気がしないから。
「いいえ」だと思うのは、専業主婦としての環世界の壁は、自分が指先を引っ掛けて登れる壁のように見えるから。
家事、育児、整理収納、人づきあい、ブログ…
充分に工夫のしどころはあるし、ここで私は成長していける気がしている。
私は、「考える、調べる、書く」ことが好きで、このことをしている間は退屈ではないです。
「考える、調べる、書く」ことがうまくできてると、成長していける気がするんです。
当たり前だけど、「考える、調べる、書く」ことはワーママの専売特許じゃない。
専業主婦であっても「考える、調べる、書く」ことは十全にできるんだ、という当たり前のことに気づけて、私は「専業主婦の日々の生活で疲れても、また回復して成長できる見込み」を感じてる。
退屈は、忌むべきものじゃなくて
前述のハイデッガーのいう退屈は第三形式というものがあるそうで、
③なんとなく退屈だ。
というのがそれなんだそうです。

なんとなく!!
日常生活のなかで、ふと、「なんとなく退屈だ」という声が聞こえてくることがあるのではないか、と、ハイデッガーは言っているのである。
そして、その声が私たちの心の底から聞こえてくるのであれば、どうやってもそこに耳を傾けないわけにはいかないではないか、と言っているのである。
(『暇と退屈の倫理学』p.246)
もうこうなってくると、お手上げです。
専業主婦だろうがワーママだろうが、どう生きたって、退屈からは逃れられないわけだよねえ。
だとしたら、退屈は、排除し、退けるべきものではなくて。
退屈は、定期的に訪れるステータスなのかな。生理みたいなもの。
つきあい方、やり過ごし方を知ってうまく付き合ったほうがいいものなんだろうねえ、と思いました。
退屈だと、退屈をどうにかしようとする。
退屈な「今、ここ」からもがこう、出ようとするパワーが生まれる。
退屈を打ち消そうと思って、なんとか退屈状態を解除しようと、自分の内外を検索するような力が沸きがちなので、創造力の母なのかもしれない。
そんな考え方をどこかで見たな…、と思い出したのは、クラタイクツさんの自己紹介だった!
「あー退屈だな〜」と思うとき人は、「自分をもっと楽しませたい」と言うエネルギーに満ちていると思います。
「現状が退屈である」というのは裏を返せば、「もっと自分を楽しませることができる」という自信、もしくは希望の現れです。
私にとって「退屈」は「次の娯楽を考える準備体制に入りました」と言う合図であり、生きている上でもっともワクワクする瞬間なのです。
(タイクツさん、急にすいません。ハイデッガーと並べて…。)
そういえば、退屈は、自分プロジェクトの推進力ともいえるものかもしれない。
で、どうするか
子育て中心の日々を「退屈」と思っているなんて、世間や子ども自身が聞いたら「えー」と思うだろう。
でもそうなんだから、仕方ない。
退屈を感じているのに、また、ハイデッガーによると、そもそも人間がどう生きたところで退屈からは逃れられそうにもないのに「全然退屈じゃないよ」と偽られているほうが、私はイヤだ。
どうやったら少しでも退屈みが薄れるかを研究して実践するのがいいんだろうな、という気がしてる。
何とか面白おかしく過ごす方法を見つけたい。
専業主婦の先輩の薄井シンシアさんのインタビューに、ヒントがありました。
娘が3歳の時、NY駐在になりました。
私は美術館鑑賞が大好きだし、NYにはたくさん素晴らしい美術館があるから行きたいけれど、ほとんどの子供は絵には興味ないでしょう?(笑)
だから美術館に行く時は、初めにGallery Shop(おみやげ屋)に行くことにしていました。
そして絵葉書を10枚くらい買って「今日はここで宝探しゲームね!」と子供に渡して、美術館で絵を探すゲームをするんです。
そうすると私もゆっくり美術鑑賞ができるし、子供も楽しく美術館にいる事ができる。
結果的にこのゲームは、娘が芸術に興味を持つきっかけになりました。だから娘は絵だけではなくてオペラなどいろいろな芸術に造詣が深いんです。
それは今まで、「子供だから連れて行くのは無理」と諦めないで、自分の好きな事をするために工夫したことの影響が大きいと思っています。

脱帽のアイディア…!
どうせ退屈は生まれるなら、それをクリエイティブの母にしないと、もったないな。
シンシアさんみたいに。
そして私も専業主婦が退屈なんて言ってないで、もっともっと楽しもう。
どうしたら、もっと楽しいのか考えよう。
ま、難航するし、どうせまた退屈に追いつかれてしまうんだけど、そしたらまたそのとき、自分にあった退屈の解消の仕方をのらりくらり考えればいいかな。
終わりに…一行感想
退屈は不治の病だけど、死に至る病ではないみたい。
むしろこの退屈とどう付き合うかが、人生の質(というものがあるなら)を左右するのだろうな、という気がしました。
うん…うまく付き合っていこう。
▼「もったいない人」に見えるみたいです▼
▼読書会をしたきっかけ▼
▼今回読んだ本▼
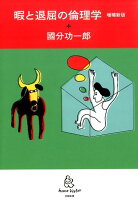 |
國分功一郎 太田出版 2015年03月 売り上げランキング :
|
今日もいい一日になりますように!

